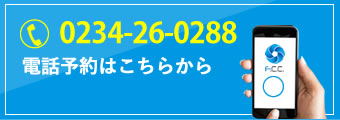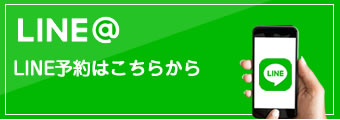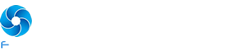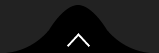こんにちは!
酒田みなみ整骨院です!
前回は、エコー撮影(超音波検査)のメリットについてお話ししましたが、今回はその具体的な使い方や、治療との連携について詳しくご紹介します。エコーは治療の質を高めるだけでなく、患者さんの安心感や理解を深めるためにも非常に役立つツールです。
エコー撮影の基本的な使い方
整骨院では、主に以下のような手順でエコー撮影を活用します:
初診時の評価
患者さんがケガをした原因や痛みの場所を確認し、エコーを使って内部の状態をチェックします。
例:足首の捻挫
靭帯の損傷や腫れの状態を画像で確認し、軽度か重度かを判断します。
治療方針の決定
エコー画像をもとに、治療の方針を具体化します。たとえば、腱の炎症が見られれば負担を減らすためのテーピングを提案したり、腫れがひどい場合は冷却と安静を指導します。
経過観察
治療の過程でエコーを定期的に使用し、患部の回復具合を確認します。これにより、回復の進行に応じて治療内容を調整できます。
例:肉離れ
治療開始から2週間後にエコーで筋肉の状態を確認し、負荷を増やしても良いかを判断します。
リハビリとの連携
回復期にはエコーを使って筋肉や靭帯の動きを確認しながら、適切なリハビリメニューを提案します。
エコー撮影が役立つ具体例
以下のような症状やケガに対して、エコーは特に効果を発揮します。
捻挫
足首や手首の捻挫時、靭帯や腱の状態を確認できます。損傷の有無だけでなく、程度を把握することで治療の優先度を決定します。
腱鞘炎
手首や指に起こる腱鞘炎では、炎症の広がりを画像化し、炎症を抑えるための具体的なケアを行います。
筋肉の損傷
肉離れや筋膜の損傷をエコーで可視化し、回復段階に応じた治療とリハビリを提供します。
関節の異常
肘や膝の滑液包炎、肩の腱板損傷など、関節周辺のトラブルの診断と治療計画に活用します。
治療との連携:具体的な例
エコーは単なる診断ツールではなく、治療の指針としても役立ちます。以下はその具体例です:
テーピングや固定法の選択
損傷箇所や程度をエコーで確認し、必要に応じてテーピングやサポーターを活用します。これにより、患部を適切に保護しながら治療を進めます。
物理療法の適用
電気治療や超音波治療を行う際、エコーで炎症箇所を特定することで、効果的な治療が可能になります。
ストレッチやエクササイズの提案
患部の状態に基づき、エコー画像を参考にリハビリ内容を個別にカスタマイズします。
まとめ
整骨院でのエコー撮影は、診断の正確性を高めるだけでなく、治療の質を大きく向上させるツールです。
初診時の評価、経過観察、リハビリメニューの策定など、さまざまな場面で活用できます。これから整骨院をご利用される際には、「エコーで詳しく見てもらえますか?」と聞いてみるのも良いかもしれません。
酒田みなみ整骨院ではご予約の方を優先してご案内しております。
先ずはお電話もしくはLINEでのご予約をお願い致します。
| 名称 | 酒田みなみ整骨院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒998-0828 山形県酒田市あきほ町120-1イオン酒田南店1階 |
| 電話番号 | 0234-26-0288 |
| 休診日 | 年中無休 |
| 診療時間 | 09:30~20:00 |
| LINE | https://lin.ee/zPKNeJa |
| https://www.instagram.com/f.c.c._sakataminami/ | |
| アクセス方法 | 酒田駅より車で約10分 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |