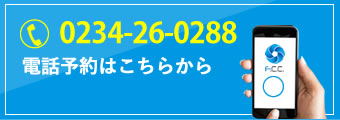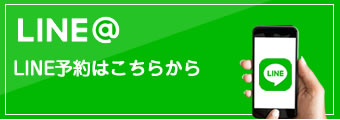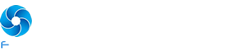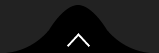こんにちは、整骨院のブログへようこそ!今回は「斜角筋症候群」についてお話しします。斜角筋症候群は、首の筋肉が神経や血管を圧迫することで起こり、肩こりや手のしびれなどを引き起こす症状です。特にデスクワークやスマートフォンの使用が多い方に見られ、放置すると日常生活に支障をきたすこともあります。この記事では、斜角筋症候群の原因や症状、整骨院での治療法、そして再発を防ぐための予防策を詳しく解説します。
1. 斜角筋症候群とは?
斜角筋は、首の前側から鎖骨の近くにかけて位置する筋肉群です。これらの筋肉が硬直して緊張することで、腕に向かう神経(腕神経叢)や血管が圧迫され、「斜角筋症候群」と呼ばれる不調が発生します。斜角筋症候群は、胸郭出口症候群の一種で、肩や腕、手にかけてのしびれや痛みが特徴的です。
2. 斜角筋症候群の原因
① デスクワークや長時間のスマホ使用
長時間同じ姿勢でいると、首や肩の筋肉が硬くなり、斜角筋が緊張して神経や血管を圧迫することがあります。
② 猫背やストレートネック
悪い姿勢が続くと、首や肩にかかる負担が増し、斜角筋に過度な負担がかかります。特に、首が前に突き出た姿勢(ストレートネック)は斜角筋を硬直させる要因となります。
③ 肩や首の筋力不足
首や肩の筋肉が弱いと、正しい姿勢を維持できず、斜角筋に無理な負荷がかかります。
④ 重い荷物を片方の肩で持つ
片側ばかりに負担がかかると、斜角筋に偏った負荷がかかり、筋肉が硬直する原因になります。
⑤ 寒さによる筋肉の硬直
寒い環境にいると筋肉がこわばりやすくなり、斜角筋の緊張が増すことがあります。
3. 斜角筋症候群の症状
斜角筋症候群の症状は、首だけでなく肩や腕、手にまで広がることがあります。代表的な症状は以下の通りです。
首から肩、腕にかけての痛みやしびれ
→ 長時間の作業後に悪化することが多いです。
手や指のしびれ
→ 神経の圧迫によって、手先の感覚が鈍くなったり、ピリピリとしたしびれを感じます。
肩こりや首こり
→ 肩や首の筋肉が硬くなり、こりや張りが慢性化します。
腕のだるさや力の入りにくさ
→ 重い物を持ったり、手を上げたりするのが難しくなることがあります。
冷えや血行不良
→ 血管が圧迫されることで、腕や手の冷えが感じられることもあります。
4. 整骨院での治療法
斜角筋症候群は、筋肉の緊張をほぐし、神経や血管の圧迫を解消することが治療の目的です。整骨院では以下の施術を組み合わせて症状の改善を目指します。
① 手技療法(マッサージ)
斜角筋や肩、背中の筋肉を丁寧にほぐし、筋肉の緊張を和らげます。これにより、神経や血管への圧迫が解消され、痛みやしびれが軽減します。
② 骨格矯正(姿勢矯正)
猫背やストレートネックの改善を目指し、首や背骨の歪みを整えます。正しい姿勢を取り戻すことで、斜角筋への負担を減らします。
③ 電気治療
低周波や超音波を使った電気治療は、深部の筋肉を緩め、血流を促進する効果があります。慢性的なこりや痛みに有効です。
④ テーピングやサポーターの使用
肩や首への負担を軽減するため、テーピングやサポーターを使ってサポートします。日常生活での負担を減らし、回復を促します。
⑤ ストレッチとエクササイズの指導
斜角筋をほぐすストレッチや、肩周りの筋力を強化するエクササイズを指導します。筋肉を柔らかく保つことで、再発を防ぎます。
5. 自宅でできる斜角筋症候群の予防策
① 正しい姿勢を保つ
デスクワーク中は背筋を伸ばし、首が前に出ないようにしましょう。
画面を目線の高さに合わせ、肩をリラックスさせることが大切です。
② こまめにストレッチを行う
長時間同じ姿勢を取らないようにし、1時間ごとに休憩を取りましょう。
首や肩を回すストレッチを日常的に行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。
③ 適度な運動を取り入れる
ウォーキングや軽い筋トレで体を動かし、筋力を維持しましょう。
肩甲骨周りをほぐす運動が効果的です。
④ 体を冷やさない
首や肩が冷えると筋肉が硬くなるため、寒い季節はマフラーやストールを活用しましょう。
⑤ 負担のかからない生活習慣を心がける
荷物を片側だけで持たないようにし、体にかかる負担を分散させましょう。
重い物を持ち上げるときは、腰や足を使って持ち上げ、首や肩に無理な力をかけないようにしましょう。
6. まとめ
斜角筋症候群は、首や肩の筋肉の緊張が原因で発生するため、日常生活での姿勢や生活習慣が大きく影響します。整骨院では、手技療法や姿勢矯正、電気治療などを通じて、根本的な改善を目指します。しびれや痛みが続く場合は、早めのケアが大切です。
ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!
斜角筋症候群を改善し、痛みのない快適な生活を取り戻しましょう!
酒田みなみ整骨院ではご予約の方を優先してご案内しております。
先ずはお電話もしくはLINEでのご予約をお願い致します。
| 名称 | 酒田みなみ整骨院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒998-0828 山形県酒田市あきほ町120-1イオン酒田南店1階 |
| 電話番号 | 0234-26-0288 |
| 休診日 | 年中無休 |
| 診療時間 | 09:30~20:00 |
| LINE | https://lin.ee/zPKNeJa |
| https://www.instagram.com/f.c.c._sakataminami/ | |
| アクセス方法 | 酒田駅より車で約10分 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |